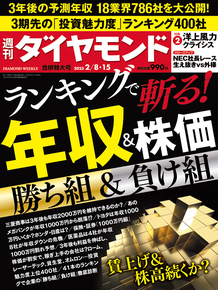記事一覧:特集10409件
-
特集 Part4
地図を通して理解する 国ごとの世界観と行動原理
2016年02月13日号一国の地理を把握すれば、その国の外交政策が理解できる──。19世紀前半のフランス初代皇帝、ナポレオン・ボナパルトの名言だ。フランス革命後の混乱を収拾し、わずかな期間でヨーロッパ大陸の大半を勢力下に置いたナポレオンの力の源泉は、その地政学的な洞察力にあった。
-
特集 Part4
【イスラエル】 周囲を囲むイスラム勢力 弱まる米国の後ろ盾
2016年02月13日号3000年前はユダヤ人が治めていたイスラエル地域。歴史の流れの中でユダヤ人(ユダヤ教徒)たちはこの地を追われ、16世紀のオスマン帝国以降は、イスラム教徒の住む地になっていた。第1次世界大戦時、英国がユダヤ人とアラブ人の両方に、この地での独立国家樹立を餌に戦争への協力を持ち掛けた「三枚舌外交」が、現在まで続く対立の原因だ。
-
特集 Part3
出口治明(ライフネット生命保険会長兼CEO)インタビュー
2016年02月13日号今や必須教養となりつつある地政学だが、何から始めればいいのか分からない人も多いだろう。ビジネス界きっての教養人であるライフネット生命の出口治明会長に、そのこつを教えてもらった。
-
特集 Part3
【Column】 “温暖化米”開発ラッシュで コシヒカリ生産農家の危機
2016年02月06日号1956年に生まれた「コシヒカリ」。人気、生産量共に日本一を誇る王者ブランドだが、近年、その地位を脅かすライバルが台頭している。
-
特集 Part5
JA解体までの猶予は5年 ラストチャンスの農協改革
2016年02月06日号JAグループを束ねるJA全中の解体は農協改革の序章にすぎない。改革のゴールは、地域農協を農業振興という原点に回帰させることだ。それができない農協には解体の道が待っている。
-
特集 Part5
支持率トップは北海道 期待度トップは佐賀県
2016年02月06日号400の地域農協に対する評価を集計し、東京を除く46道府県の「支持率」と「期待度」でランキングした。JA支持率ランキングで圏外となった地域農協などへの注文も盛り込んだ。
-
特集 Part5
127農協を独自指標で評価 首位JAいなばの“お節介力”
2016年02月06日号いまや、農家が農協を選ぶ時代である。本誌では、担い手農家が格付けした「JA支持率ランキング」を作成した。農家に寄り添った農協と、そうでない農協との格差が浮き彫りになった。
-
特集
儲かる農業
2016年02月06日号農政改革の敢行、TPP合意で始まる貿易自由化、農家の世代交代──。ニッポンの農業が大きな節目を迎えている。農協が牛耳る農業から生産者・消費者の双方がトクをする“儲かる農業”へ生まれ変わろうとしているのだ。経営感覚のある農家、就農希望者、農業参入を目指す企業にとって、千載一遇のチャンスが訪れている。
-
特集 Part1
【Column】 護送船団方式をぶっ壊せ 小泉氏に問われる実行力
2016年02月06日号1月18日、自民党の農林水産業骨太方針策定プロジェクトチームの会合に参加した農協関係者の表情が青ざめる一幕があった。
-
特集 Part1
【本誌独占インタビュー!】 小泉進次郎が挑む「農政改革」三つの公約
2016年02月06日号農業を儲かる産業へ変える──。将来の首相候補との呼び声が高い小泉進次郎衆議院議員(自民党農林部会長)が立ち上がった。これまで、政府与党が幾度となくトライしながらも農林族らの抵抗で頓挫してきた「農政改革」に、本気で挑もうとしている。その小泉氏が、大手メディアとしては初めて本誌の単独インタビューに応じた。取材は昨年末と今年1月末の2回。肉声で語られる“小泉流農政改革”の全貌とは何か。三つの公約と共に明らかにする。
-
特集 Part2
農家1925人の頂点に立つ モデル農家ベスト20の実力
2016年02月06日号農業を儲かる産業へ──。遅ればせながら、政治が動き始めた。農業の“健全化”が進むことは、経営マインドのある農家にとっては渡りに船だ。攻めに転じる大チャンスが訪れている。
-
特集 Part2
【秘訣(1)経営ビジョン】 農水省もまっ青な目標設定と 堅実な収益モデルが強み
2016年02月06日号昨年12月、みぞれ交じりの雨が降りしきる中、石川県北部の能登半島を訪れた。典型的な中山間地域である能登半島だが、実は、数十ヘクタールから百ヘクタール規模での企業の農業参入が相次いでいる。
-
特集 Part2
先輩農家に学ぶ成功の鍵は 経営者の才覚と「五つの秘訣」
2016年02月06日号農業の魅力は、経営者が自身のカラーを打ち出しやすいこと。農業で成功する要素として、経営者の才覚は欠かせない。モデル農家の成功例から、五つの秘訣を導き出した。
-
特集 Part2
【秘訣(2)コストダウン】 きっかけは母と競った原体験 驚異のコメ生産費44%カット
2016年02月06日号政府は10年間で、コメの生産費を4割下げ、1俵(60キログラム)当たり9600円にする目標を掲げる。だが、それを上回るコスト削減を実現し、補助金がなくても成り立つ経営をしているコメ農家がいる。茨城県龍ケ崎市の農業生産法人「横田農場」だ。
-
特集 Part2
【秘訣(3)販路の確保】 30年ごしの大ヒット商品 超高級おせちがばか売れ
2016年02月06日号石川県の農業生産法人「六星(ろくせい)」の厨房は毎年、大みそかに戦場となる。総菜部門の精鋭20人が、おせち料理400セットを一気に盛り付けるからだ。
-
特集 Part2
【秘訣(4)農産物・地域のポートフォリオ】 野菜40品目と飛び地農法が 可能にした「リスク分散」
2016年02月06日号群馬県の農業生産法人「野菜くらぶ」の歴史は、事業の多角化の歴史だといっても過言ではない。原点は1980年代にさかのぼる。野菜くらぶの澤浦彰治社長は、コンニャク相場の大暴落に見舞われ、破産状態に追い込まれていた。90年、経営を安定させる方策として、コンニャクの加工を始めたのが、多角化への第一歩だった。
-
特集 Part2
【Column】 野菜工場も実は技術者しだい 業界トップ「茨の道」の再出発
2016年02月06日号国内最大級の野菜工場を運営する農業ベンチャー「みらい」が、昨年6月、破綻した。本来、野菜工場では、天候に左右されることなく、均一に野菜ができるものだ。しかも、同社のシステムは太陽光を使わず、人工光で野菜を育てるため、なおさら外部環境の変化を受けにくいはずだった。
-
特集 Part2
【秘訣(5)人材の育成】 マネジャーの給料は70万円! 農業でも能力給が当たり前に
2016年02月06日号農業界で、マネジャーの人材争奪戦が激化している。生産技術に精通しており、現場のマネジメントもできる人材が足りないのだ。
-
特集 Part2
【Column】 広がる地元産米への回帰 日本酒1日1合が農業を救う
2016年02月06日号酒造りと稲作。いったんは離れ離れとなった両者が、今、再び仲直りしようとしている。その背景には、ワインへの対抗、消費者の嗜好の変化や、輸出機会増大という好機がある。
-
特集 Part3
韓国産パプリカを国産に転換! 伸びる農産物「五つの条件」
2016年02月06日号何を作れば稼げるのか──。この問いは、農家にとって永遠の課題だ。100%の正解はないにせよ、一歩進んだプロ農家は今、どんな農産物を“種まき”しようとしているのだろうか。