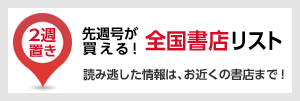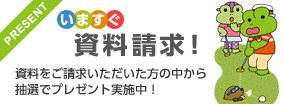退職金格差が拡大中
今、退職金に恐るべき三つの激変が押し寄せている。
一つ目は「金額の激減」だ。なんと、20年前に比べて平均で1000万円以上も減った(厚生労働省統計)。企業年金の給付利率も下がるなど、退職金の減少はとどまるところを知らない。
二つ目の激変は「自己責任」化。その象徴の一つが「確定拠出年金」の拡大だ。
あらかじめ支給される額が決まっている「確定給付企業年金」などとは異なり、確定拠出年金とは、定められた拠出額を基に、労働者自身が運用を行うというもの。自身の運用次第で受け取れる額が変わる、いわば 〝自己責任〟の仕組みだ。
「確定給付から確定拠出への流れは、会社が運用リスクを取らなくて済むので、今後も進んでいくだろう」と断言するのは、りそな年金研究所の統括主席研究員である谷内陽一氏。確定給付企業年金が企業にリスクを負わせる制度だとしたら、確定拠出年金は個人がリスクを負うものであり、企業から個人への責任の転嫁が進む。
出世による違いが顕著になる
三つ目が「出世圧力」だ。というのも、いまや退職一時金の制度の過半を占める「ポイント制」は、どれだけ出世したかが大きく退職金額に影響するからだ。
ポイント制とは、在職時の役職や勤続年数などを基に計算されるポイントの累計を基に退職金額を決める制度。早くから上位の役職に就くことでポイントが増し、そうでない人との差が大きく開く。
人事コンサルティング企業、ベクトルの秋山輝之副社長は、「かつてであれば、企業内で標準額から±15%ぐらいの範囲に退職金額が収まっていたものが、いまは±50%ほどの差が生まれるようになり、格差が大きくなっている」と説明する。
今回、週刊ダイヤモンドでは、本誌定期購読者およびダイヤモンド・オンライン会員に向けて1000人を超える大規模なアンケートを実施した。そこで明らかになったのは、驚くべき格差の実態であった。
最終役職別の退職金額の平均を算出したところ、一般職級が1664万円に対して、部門長・部長級が2701万円、社長・役員級に至っては3095万円と、実に1000万円以上の開きが出たのである。

退職金が0という人も存在
図を見ると、主任・係長級と課長級の間で開きが大きくなっている。やはり、退職金額には、管理職になるかならないかという昇進の壁が厳存するようだ。