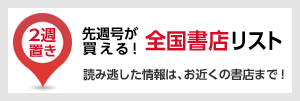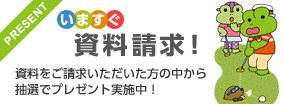株式市場にとって、やはり「10」という数字は鬼門なのか――。
今から約30年前の1987年10月19日、米ニューヨーク証券取引所のダウ工業株30種平均の終値は、前週末より508ドル下落した。いわゆるブラックマンデーだ。
株価の下落率は22.6%に達し、世界恐慌の引き金となった1929年の暗黒の木曜日、ブラックサーズデーの下落率12.8%を大きく上回った。この翌日にはアジア各国の市場に危機が伝播、日経平均株価は14.9%下落し、3836円安の2万1910円と過去最大の暴落となった。
その10年後の97年。運用チームにノーベル経済学賞受賞者たちをそろえ、高度な金融工学理論を駆使していた米ヘッジファンド、ロングタームキャピタルマネジメント(LTCM)が破綻した。
巨大なレバレッジを掛けた運用を行っていたために、アジア通貨危機による相場の大変動を吸収できず、ドリームチームと呼ばれたLTCMは設立からわずか5年で姿を消すこととなった。
そして、さらに10年後の2007年には、フランス・パリに本拠地を置く世界有数の金融機関、BNPパリバを発端とするサブプライム問題が勃発。翌08年9月のリーマンショックを引き起こしたことは、いまだ記憶に新しい。
こうした株式市場を大きく揺るがす金融危機は、「10年周期」で訪れることが多い。そうした意味でいえば昨年、18年は過去に比べれば規模は小さいながらも、2度のクライシスが起きている。
米長期金利に端を発した2度の株価急落
フラッシュクラッシュを起こした為替変動
1度目は、2月に起こった「VIXショック」と呼ばれるものだ。
米長期金利の指標となる10年物国債利回りが、4年3ヵ月ぶりに3%を超えたことを受けて、世界的な株価急落が発生。日経平均は2月6日、1071円の大幅下落となった。
併せて、「恐怖指数」と呼ばれる米株式市場の予想変動率を示すVIX指数が投資家の予想をはるかに上回り、多額のロスカットを強いられることとなった。
そして2度目は、10月初旬のことだ。10月2日、日経平均は91年11月以来、約27年ぶりとなる高値の2万4270円を付けた。翌3日には続伸するNYダウが、過去最高値となる2万6828ドルまで上昇した。
さらなる高値を予想し、楽観ムードに支配されていた市場が凍り付いたのは、その直後のことだ。
米長期金利が3.23%と約7年4ヵ月ぶりの水準に急上昇したことで、NYダウが831ドル下落。日経平均も10月11日には、一時1000円余りも下げた。金利上昇に加え、米中貿易摩擦の激化による先行き不透明感の高まりなども株価下落に拍車を掛けた。
その後、株価はいったん持ち直したものの12月に入ってから再び大幅に下落。NYダウは12月頭から最安値を付けた25日の下落幅が3700ドルを超え、つられて日経平均も3400円以上下がり、2万円の大台を割り込んだ。
通常、米国では、12月はクリスマス休暇があるなど動きは少ないが、そうした過去の経験則とは関係なしに株価が激変したことに、市場は動揺を隠せなかった。
さらに年始には為替が大きく動いた。1月3日の午前7時半すぎ、外国為替市場で円相場に異変が起きたのだ。それまで1ドル=108円台後半で推移していた円相場が、わずか数分程度の間に約4円も急騰。いわゆる「フラッシュクラッシュ」と呼ばれる現象だ。
昨年末の株価急落とともに、そもそも流動性が少ない時期に、人工知能(AI)を搭載した機械取引による円買いが、円の急伸を引き起こしたとされる。
昨今、AIによるアルゴリズム取引の急増に加え、中央銀行の超金融緩和による巨額マネーの供給、世界的なインデックス投資の拡大による市場のゆがみなど、相場の常識は通用しづらくなっている。特集では、子細に市場を分析し、相場の“新格言”を導き出していく。
機械取引と金融緩和が支配する相場
変わった常識を「新格言」として提示
『週刊ダイヤモンド』3月30日号の第1特集は「株・為替の新格言」特集です。
昨年の2度の株価急落で、長らく続いた適温(ゴルディロックス)相場は終わったとの見方が広がりましたが、年明けにパウエルFRB議長が利上げを据え置くという主旨の発言をしたことで、市場は再び落ち着きを取り戻しました。
つまり、超金融緩和が相場に与える影響の大きさが改めて浮き彫りになったわけですが、その一方で、短期間での変動幅の大きさがアルゴリズムによる機械取引によるものでは、との見解が広がっており、相場には不信感が広がっています。
いずれにせよ現在の相場は、過去の常識が通じにくくなっています。そうした相場の注目ポイントを分析し、これまでの常識が変わった点を「新格言」として落とし込み、提示しました。