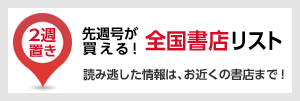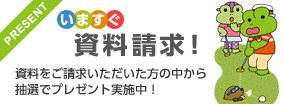40代の主婦はある日、ファイナンシャルプランナー(FP)の元を訪れていた。月額の保険料が「あまりに高い」と感じ、保険を見直したいと考えたからだ。
聞けば、夫が20代で結婚したての頃、保険の営業員から「結婚したのだから保険くらい入っておかなければ駄目よ」と言われたのをきっかけに、勧められるままの保険に入ったという。
それ以降も、別の保険に入ったり、営業員に言われたとおりに契約を更新したりした結果、いつのまにか月の保険料が4万円を超え、さすがに「無駄なのではないか」と感じたのだという。
相談を受けたFPは、生命保険最大手が販売した定期付き終身保険の保険証書を目にし、愕然とした。というのも、定期保険部分の保険料払込満了がなんと「102歳」になっていたからだ。
しかも、どの保険も契約更新のたびに、保険料が引き上げられていた。FPが「これは完全に保険会社のカモになっていますよ」と伝えると、主婦は「やっぱり」とため息を漏らしたという。
この夫婦のみならず、自分がどんな種類の保険に入り、契約内容がどうなっているのか、理解しないまま保険料を払っている人たちは多い。
しかし、これが住宅であれば複数の物件を比較したり、何度も下見をしたりするなど検討を繰り返すだろう。「住宅は高いから」と言う人もいるが、保険も一生涯で支払うトータルの保険料でみれば相当なものだ。
生命保険文化センターによれば、1世帯当たりの年間保険料は最新のデータで41万6000円。30年間に渡って払い続けたとすると1248万円、40年間なら1664万円に上る計算になり、住宅の次に大きな買い物といえる。
にもかかわらず「日本人は、保険を“安心”や“お守り”といった感情で捉えてしまいがち。だから、不安をあおりながら勧めてくる営業員の口車に乗 せられて、必要以上の保険に入ってしまっている」と指摘するのは、辛口の保険評論家で知られるファイナンシャルプランナーの長尾義弘氏だ。
長尾氏によれば、保険の本来の役割は、「万が一のときの経済的損失を補うためのもの」。だから、「経済合理性で考えるべき」で、「必要な保障は確保しつつ、無駄は見直して家計の負担を軽くすべき」と訴える。
では、「必要保障額」とはどの程度のものなのか。簡単に言えば、遺族の生活費や教育費、住居関連費などを足した「支出」から、遺族年金や貯蓄、妻 の収入といった「収入」を引いて、それでも足りない金額のことだ。保険は、この部分を賄う範囲で入ればいいと長尾氏は言っているのだ。
しかし、「入院が必要な大きな病気をしたときに困るではないか」という声もある。しかし心配はご無用。多額の医療費がかかったときに一定額を超えた分が後から返ってくる「高額療養費制度」というものがあるからだ。
たとえば100万円の医療費がかかった場合、窓口で支払う自己負担は3割(70歳以上の一定所得以下の場合は2割)だから30万円。しかし、この 制度を使えば、年収が370万~770万円の人の場合21万2570円が返ってきて、最終的な自己負担はわずか8万7430円となる。
しかも、である。1年間に3回以上の高額療養費の支給があると、4回目からは「多数該当」という制度が適用され、4万4400円以上は払わなくて済むのだ(所得に応じて金額が変わる)。
つまり、「100万円程度の貯蓄があれば、なにも保険に頼る必要はない」(長尾氏)のである。時折、保険のパンフレットなどで、「入院すると○十万円」などと書いてあるものもあるが、高額療養費制度を加味していないケースも多いから注意が必要だ。
一方、「医療保険に入っていたから、かかった入院費用に10万円程度プラスした保険金が支払われてもうかった」といったケースも良く聞く話だ。
しかし、払い込んだ金額を考えてもらいたい。20年など長期に渡って合計100万円以上の保険料を払っていれば、10万円程度プラスになってもたかがしれているのである。
このように、合理的に考えれば無駄な保険はたくさんある。一度入ったらほったらかしにするのではなく、その中身をしっかりと確認し、自分に合った形で見直すことが重要だ。