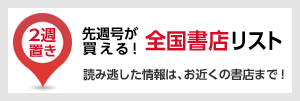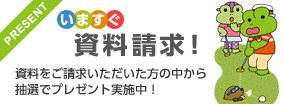コスト削減と規模の論理が
小売り原理主義のイオンの農業
手法こそローソンと百八十度異なるが、同様に農業のビジネス化を加速させているのが、冒頭にも登場した小売り大手のイオンだ。
100%子会社のイオンアグリが直営の「イオン農場」を展開している。ローソンが生産を農家に任せているのに対して、イオンアグリは農場での生産を社員自らが行っている。
こうした社員農業というやり方には賛否両論あり、農業に参入している企業からさえも、「人事異動のある社員が野菜を作っても、うまくいくはずがない」と冷ややかな声が聞こえてくる。
それでも、イオンアグリの福永社長は「経営の考え方で既存の農業関係者と意見を共有することは、できないかもしれない」と意に介さない。
さらにイオンアグリは、富士通のITクラウドサービス「Akisai」を採用。農場内に設置されたセンサーで収集したデータを駆使して、丼勘定だった農業のコスト構造を把握し、コスト削減を徹底している。
福永社長は「無駄がどこにあって、どう効率を上げていくべきか。もっとコストを下げられないのか。小売り的な発想で、キャベツ1個の生産原価にもこだわっていく」。
過去の企業の失敗から、農家主体になっていた生産にまで入っていき、ノウハウを根こそぎ収集することで、ブラックボックスだった農業の生産を徹底的に「見える化」していくという。
「安全でより安い商品を消費者に届けたいから」と福永社長。小売り原理主義ともいえるイオンらしい経営戦略だ。
小売りの厳しいコスト管理が農業に定着すれば、農業の産業化は加速するはずだ。しかし、それは農家にとって居心地の良いものではないのかもしれない。農業の丼勘定はある意味でおおらかな経営と表裏であり、それがなくなれば、牧歌的な時代に戻ることはできない。ただし、政府が声高に叫ぶ農業の6次産業化は、それなくして実現できないことも事実だろう。
イオンの狙いは、農業の「見える化」によるコスト削減にとどまらない。
「日本最大の巨大農家」──。徹底したコスト削減と規模の論理の追求。これこそがイオンの見据える農業ビジネスだ。
その発想の中で、冒頭の1000ヘクタールもの農地申請があったというわけだ。埼玉、千葉での農地バンクへの申請を合わせると1350ヘクタール。当然、申請した全ての面積を借り受けられるわけではない。それでも、拡大路線を突き進む経営スタイルは、農業関係者にとっては脅威で、業界ではさまざまな臆測が飛び交っている。
足元では、米価が急落しており、コメ農家の大量離農が起こって、耕作放棄地が一気に増える可能性が指摘されている。
埼玉、千葉、兵庫などで「大量の耕作放棄地を借り受けることで、農地集約を一気に進めて、コストダウンを図ろうというのがイオンの戦略だろう」と別の小売り大手幹部は予測する。
イオンは、他の自治体でも政府の農地バンクを積極的に活用する方針だ。農地バンクへの耕作放棄地の集積は時間がかかるとみられていたが、大量離農に伴って想定以上に進めば、日本一の農家という言葉が現実味を帯びてくる。