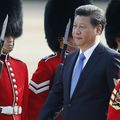記事一覧:News & Analysis15件
-
News & Analysis
いまや世界経済最大のリスク 中国GDP成長率が7%割れ
2015年10月24日中国の景気減速が続いている。今年7~9月期の実質GDP成長率が6.9%と、ついに7%を割り込んだ。8月には、突然の人民元切り下げで中国経済に対する見方が一気に悲観的になり、世界同時株安を引き起こしたことは記憶に新しい。果たしてこの数字を市場はどう評価したのか。
-
News & Analysis
中国減速で米利上げ先送り マーケットの混乱は続く
2015年9月24日米連邦準備制度理事会(FRB)は、9月の米連邦公開市場委員会(FOMC)で、利上げを見送った。9月の利上げを予想してきた大川智宏・UBS証券エクイティ・ストラテジストは、「利上げの先送りで、金融市場の不透明感が増してきた」と指摘する。FOMC後、日経平均株価も米ニューヨークダウもじわじわ下落した。
-
News & Analysis
株式時価総額で世界第2位 上海株急騰の意外な"真犯人"
2015年4月23日中国・上海株が急騰している。上海総合指数は4月22日に4300を超え、ここ1年足らずの間で2倍以上に伸びた。中国経済が減速している中、なぜ株価は上がっているのか。バブルの前兆ではないのか。上海株急騰を後押ししている意外な"真犯人"を明らかにする。
-
News & Analysis
無資源の島を繁栄国家へ シンガポール建国の父逝く
2015年3月26日3月23日未明、アジアを代表する稀代の政治家がこの世を静かに去った。シンガポール初代首相のリー・クアンユー(Lee Kuan Yew、李光耀)氏は、資源も伝統もない「島」から今日の繁栄国家を築き上げた。建国の父の足跡をたどる。
-
News & Analysis
民主選挙求める香港市民 聞く耳持たぬ中国政府
2014年10月10日香港行政長官選挙から民主派候補を排除する中国政府の決定に反発した学生らが始めたデモは、最大で10万人を超える前代未聞の抗議運動となった。香港政府が強制排除をちらつかせる中、6日になって政府と学生団体との間で対話に向けた交渉が始まったが、事態は予断を許さない。
-
News & Analysis
欧米による制裁下でも 止まらない対ロシアビジネス
2014年6月3日ウクライナ情勢が悪化している。悲惨な状況が報道されるたびに心が痛む。しかし、ビジネスの観点から考えた場合、注目すべきは地域大国ロシアの動きと、それに対する欧米の制裁だろう。本稿では、3月以降のウクライナ問題を踏まえたロシア経済の現状と、中長期的展望について論じたい。
-
News & Analysis
新興国通貨不安とは一線を画す 「アフリカ堅調」の理由と将来性
2014年3月25日2013年5月に米国で金融緩和縮小観測が出始めてから、多くの新興国で通貨不安が見られた。中でも、インド、インドネシア、ブラジル、トルコ、南アフリカはフラジャイル・ファイブと呼ばれ、「経常赤字が通貨の安定性を損なう」という論理を背景に、通貨下落⇒インフレ期待⇒緊縮圧力⇒景気悪化観測⇒通貨下落という連想で、経済の悪循環に見舞われた。
-
News & Analysis
インドネシアがはまった罠
2013年11月26日インドネシアルピアの下落が続いている。ルピアを含む新興国の為替レートは、2008~09年にリーマンショックを契機に下落した後、安定を取り戻していったが、今年5月にバーナンキ・米FRB議長が量的緩和政策(QE3)年内縮小の可能性を示してから、同時下落の様相をみせるようになった。
-
News & Analysis
インドネシア変調で建機失速 政治リスクで回復の道見えず
2013年11月7日「大変厳しい半年だった。少なくとも今期中は、よい話は出てこないだろう」(藤塚主夫・コマツCFO)。建設機械メーカーが、逆風に見舞われている。特に目立つのが、コマツの不振である。同社の2013年4~9月期連結売上高は前年同期比0.6%減、営業利益は同2.1%減。2014年3月期の見通しでは、営業利益は同0.8%減となった。もともとは同44%増益を見込んでいただけに、一転しての減益予想は市場に衝撃を与えた。
-
News & Analysis
韓国経済を悩ますアキレス腱 財閥二極化、市民生活しわ寄せの影
2013年10月29日韓国経済が伸び悩んでいる。リーマンショックによって落ち込みを経験した後、回復傾向にあったものの、欧州の景気低迷や中国経済の減速をうけ、景気の低迷から抜け出せていない。2013年4-6月期は9四半期ぶりに前期比1%以上の伸びとなったものの、政府消費や建設投資が押し上げ要因となっている。足元の生産や消費関連指標も、底を打ちつつあるものの力強さに欠け、自律的な回復に繋がるには時間を要するであろう。
-
News & Analysis
ドイツ総選挙でメルケル大勝も不安 投資家が恐れるアンチ金融税制の行方
2013年9月26日9月22日に実施されたドイツ総選挙の結果に、一部の機関投資家が戦々恐々としている。結果は大方の事前予想通り、メルケル首相率いる与党の中道右派、キリスト教民主・社会同盟(CDU・CSU)が、総議席数630のうち311議席を獲得して大勝、第一党の座を守った。
-
News & Analysis
磁力増す「メコン経済圏」の勃興 出遅れた日本企業が背負う課題
2013年8月13日中国への進出ブームに陰りが出てきている傍ら、メコンブームが訪れている。UNCTADの対内直接投資統計によると、2012年の対中直接投資は1211億ドルと高水準ながらも、伸び率は▲2.3%と3年ぶりに減少に転じた。中国政府発表では、2013年に入って対中直接投資は持ち直しをみせているが、けん引役を果たしてきた製造業は減少を続けている。一方、2012年の対メコン直接投資(ミャンマー、ベトナム、カンボジア、ラオス。本稿ではタイを除く)は125億ドルと、水準はなお中国の1/10足らずだが、伸び率は+15%と回復が続いた。足元も、ベトナム、ミャンマーを中心に工場や駐在員事務所の設置が相次いでいる。
-
News & Analysis
9月のQE縮小開始は後退か 米景気評価を下げたFOMC
2013年8月2日7月30〜31日の米連邦公開市場委員会(FOMC)後に発表された声明は、米国経済拡大の評価を前回と比べて「moderate(適度な)」ペースから「modest(控えめな)」ペースに1段階下げた。
-
News & Analysis
高度成長からの“出口”を模索する 中国新政権の試練、「影の銀行」問題
2013年7月23日7月15日、中国の国家統計局は、2013年4~6月期の経済成長率が前年同期比+7.5%と、2四半期連続で減速したことを発表した(図表1)。この成長率は、リーマンショック時のボトムとなった2009年1~3月期(前年同期比+6.6%)を除くと、国有企業・国有銀行問題に見舞われデフレが続いていた2001年10~12月以来の低さであり、従来の尺度からすれば警戒水準というべきものであった。
-
News & Analysis
鮮明になった中国の成長鈍化 現実味増す7%台前半への減速
2013年7月18日「中国特需は終わった。世界は早めに現実を受け入れ、リスクシナリオを想定したほうがよい」(肖敏捷・SMBC日興証券エコノミスト)。中国経済のさらなる減速があらわになった。7月15日に発表された4~6月期の経済成長率は前年同期比7.5%増と、1~3月期の7.7%から一段と低下した。