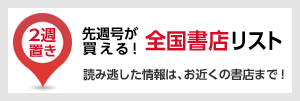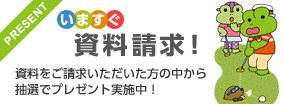継続的にキャッシュが入る「サブスクリプション」
読売新聞グループを率いる絶対的権力者、読売新聞グループ本社代表取締役主筆の渡辺恒雄(ナベツネ)氏と、世界最大手の動画配信事業者、ネットフリックスを率いるリード・ヘイスティングス氏。この2人の共通点として最初に挙げるべきは、「サブスクリプション」をビジネスモデルに採用していることだ。
ビジネスの流行語、サブスクリプション(subscription)を辞書で引いてみると、「新聞や雑誌の定期購読」「予約購読」と出てくる。読売新聞グループなどの新聞は、〝元祖サブスク〟といえる。読売新聞は朝刊と夕刊のセットで月額4400円(税込み)。これだけ払えば、自宅ポストまで新聞を届けてくれる。
ネットフリックスはスタンダードプランで月額1200円(税抜き)。契約すれば、いつでも映画やドラマ、ドキュメンタリーが見放題である。
この数年、世界中でサブスクを採用した企業が成長しており、産業界でははやりのモデルだ。ネットフリックスやアップル、アマゾンなどの米国企業の他、日本でもソニーやパナソニック、トヨタ自動車などがサブスクを採用した事業機会を模索している。
だが、新聞メディアは、はるか昔から実践してきた。
両社には、月額料金に契約人数を掛けた金額が、毎月転がり込む。ナベツネは約800万の読者を抱え、ネットフリックスは全世界で1億4000万人超の会員を抱えている。
顧客との距離を最短にした強力な「流通網」
ナベツネとネットフリックスには、それぞれ他社にはない競争力の源泉となる流通網がある。
読売新聞を率いるナベツネの持つ流通網の最大の特徴は、日本全国約7000店の販売店だ。朝日新聞や毎日新聞は、人口減少が急速に進む郊外から人口密集地の都市圏へ販売の重点を移しており、販売店数は右肩下がり。そんな中、読売新聞は日本全国、津々浦々に配達する態勢を維持。自前の販売網を死守している。それが世界最大の新聞の地位を揺るぎないものにしている。
一方、ネットフリックスは世界190カ国以上で、会員が好きなときに好きなコンテンツを、どこででも見られる体制を整えた。
コンテンツのデータ供給を支えるのは、米アマゾンのクラウドサービス「アマゾン・ウェブ・サービス」。ナベツネと違い、こちらは自前ではない。
だが、同社の自慢の技術部隊が、通信インフラの強弱に左右されずに大容量の映像データを見ることができるように、データ伝送や圧縮の技術を改善。どのような環境でも、快適に動画が楽しめる体制を整備している。
他社がまねできない「キラーコンテンツ」
コンテンツ・イズ・キング。メディア事業において最も大事なのは、コンテンツであるという意味だ。
ここ数年、一部のウェブメディアが真偽不明の情報を掲載し、社会問題に発展する事件が多発。このことがきっかけで、しっかりと裏を取る新聞など、レガシーメディアのコンテンツ力が見直されるようになった。
冒頭の言葉は、集客テクニックに走りがちなメディア業界が自らを戒める警句でもある。
だがナベツネとネットフリックスは、この言葉に注目が集まるよりもはるか前から、コンテンツの重要性を自覚。その強さを磨き上げる経営施策を進めてきた。
ナベツネは読売巨人軍という、他社が絶対に持つことができない究極のキラーコンテンツを武器に、メディア王の座を盤石にした。
巨人軍のセ・リーグ優勝36回、日本一22回は球界最多だ。長嶋茂雄氏や王貞治氏、松井秀喜氏など、国民的スター選手を輩出している。2018年の観客動員数は300万人を突破。球界ナンバーワンの座に君臨している。
このコンテンツの強さを、ナベツネは最大限に活用した。観戦チケットを定期購読者獲得のための特典にし、新聞販売部数を急拡大させる起爆剤にしたのだ。
もちろん、新聞社らしく「素晴らしい記事を書け」とグループ内でハッパを掛けるものの、実際は読売巨人軍こそが王者の切り札なのである。
ネットフリックスもキラーコンテンツの強化にひた走る。13年から独占配信作品を増やす戦略にかじを切った。積極的な投資を続けており18年にはオリジナルコンテンツに80億㌦(約9000億円)もの大金を投じた。
最大の成果が、19年のアカデミー賞で作品賞を含む10部門にノミネートされ、監督賞など3部門で受賞した「ROMA/ローマ」だった。
切磋琢磨する「良きライバル」
油断すれば追い越される。ナベツネとネットフリックスには、強力なライバル企業が常に存在した。
ナベツネにとっては朝日新聞社だ。新聞記者における最高の勲章である新聞協会賞の受賞回数は24回で、読売より10回多い。クオリティーペーパーを自任する朝日新聞は、質の面で読売にとって常に目の上のたんこぶだった。
実力差を埋めるべく、ナベツネは量で勝負に出た。ひたすら販売部数を追い求めて悲願の1000万部を達成。さらに朝日新聞にはない読売巨人軍という、大衆受け抜群のキラーコンテンツへの投資へと走ったのだ。
ネットフリックスにとっては、同時期に動画配信を始めたアマゾンの「アマゾンプライム・ビデオ」が宿敵だ。アマゾンは生鮮食品も扱う世界一のEC(eコマース)サイト。ネットフリックスにはない利益の源泉を多く持つ。
ネットフリックスが、脇目も振らずコンテンツをひたすら充実させる戦略に集中してきたのは、強力なライバルに突き動かされていたからともいえる。
敵を遠ざけ力を維持する「非情な人事」
政財界の勢力争いを探るのが仕事でもある記者は、無類の「人事好き」が多いといわれる。勢力争いを制する者は、必ず人事力を駆使する。そんな鉄則が身に染みているからか、ナベツネは自らの足場を固めるために、人事を常に意識していたといわれる。
『渡邉恒雄 メディアと権力』(魚住昭著、講談社文庫)によれば、務台光雄元社長から受け継いだ絶対権力を維持するために、マキアヴェリの『君主論』第十七章についてよく言及したという。
「君主たる者は、おのれの臣民の結束と忠誠心とを保たせるためならば、冷酷という悪評など意に介してはならない。(中略)慕われるよりも恐れられていたほうがはるかに安全である」
ナベツネはこれを実践。自身の地盤である政治部出身者を周辺に置いて権力基盤を固め、その後の部数1000万部達成へつながる組織の結束力を高めた。
ネットフリックスのヘイスティングスCEOも社内に「解雇奨励」の企業文化を植え付け、それをてこに戦略遂行力を高めてきた。DVD宅配レンタルから配信事業へと本業を転換する際には、否定的だった経営幹部5人を解雇。功労者であっても容赦しない人事を徹底し、動画配信へと一気にかじを切って成長につなげた。
新メディアは超強力周辺に与える影響も大きい
『週刊ダイヤモンド』4月20日号の第一特集は、「NETFLIXとナベツネとコンテンツの未来」です。
世界一の動画配信事業者であるNETFLIXはすさまじい勢いで成長を遂げています。映像エンターテインメントの供給は、長らくテレビ局や映画会社が担ってきました。この構造が急速に変化しつつあります。
そのNETFLIXを21世紀型メディア王とするならば、20世紀型メディア王は読売新聞グループを率いる「ナベツネ」こと渡邉恒雄氏。この2社を大胆に比較し、王者の条件をあぶり出し、コンテンツ産業の未来を見通してみました。
(ダイヤモンド編集部 片田江康男)