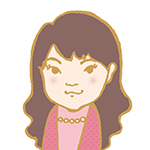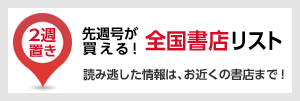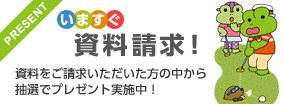サービスを「無料」で開放することで、人の欲求を素直に表す検索ワードを集め、より関心に沿った広告を打つモデルを生み出したのである。
ウェブという特性から、実際に広告がクリックされた回数など、広告効果も正確に測定でき、しかもシステムで運用するため、広告出稿のコストも劇的に下がった。
その結果、瞬く間に広告が集まるようになり、グーグルのような広告モデルのネット企業は急成長を果たす。
すると今度は、さらに興味や関心を探るため、ウェブ閲覧履歴やサービス利用履歴などの要素も加味するようになる。そのためには大量の個人データが必要。そこでネット企業は、得た収益を元手に新たなサービスを開発して無料で提供、次から次へと個人のデータを奪っていったのだ。
さらにスマホの登場によって移動履歴などのセンサー情報もため込めるようになり、広告の〝精度〟は劇的に向上した。
だが、このようなネット企業を脅かす存在が登場する。それが、
フェイスブックやツイッターといったソーシャル・ネットワーキング・サービス(SNS)である。
SNS会社は「無料」をうたい文句に利用者を呼び込み、これまで取得が難しかった実名のプロフィールや、友人とのつながりといったプライバシー色の強い情報を、ユーザー自らに登録させ、吸い上げることに成功した。
併せて、ユーザーの投稿内容も蓄積。個人の関心や当時の感情など、より個人の欲求が分かるデータを大量に集める仕組みを整えたのである。
それまでの行動ターゲティング型広告は、ネットにおける利用者の「足跡」を追っているだけで、個人の情報は匿名化され、その足跡を自ら削除することもできた。
それがSNSの登場によって、よりダイレクトに個人データを利用する流れへと向かったのである。
広告費用の85%程度が
SNS会社に落ちる仕組み
では、こうして集められた個人データが、実際にどうやってカネになっているのか見ていこう。
たとえば、大手飲料メーカーA社がSNSを活用してビール広告を打った場合をみてみる。
A社のような大手には予算枠がある。ネット広告に500万円の予算を確保したとすると、A社はまず広告代理店に相談する。
すると代理店は、フェイスブックやツイッターを利用したプロモーションを提案。その際、できる限り商品の購入層に近い人たちにアプローチするため、ターゲットを細かく絞ったメニューも合わせて提示する。
例えばフェイスブックなら「都内に住む20代の女性」というだけでなく、「あるアイドルが好き」「酒に関心がある」といった具合だ。
ツイッターであっても、「あるアイドルをフォローしている人」というだけでなく、「1週間以内にA社のことをつぶやいた人」などと、その中身まで詳細に決める。
実際に広告を配信するとき、SNSが何かをしてくれるわけではない。全てシステムで運用されるため、広告代理店は運用会社に委託する。
こうして500万円の予算規模であれば、A社のビールに関心のある層に向けて5万回程度クリックされる広告を打つことができる。このケースの場合、代理店らのマージンは7.5%。つまり、SNSに434万円、広告代理店と運用会社にはそれぞれ33万円が支払われる格好だ。
こうした広告によって、SNS会社は巨額の利益を得ているのだ。