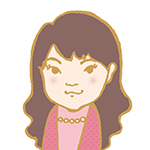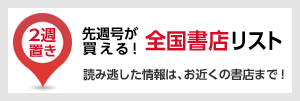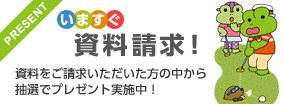「いやあ、この既視感は、半端じゃないですね……。」
ソニー本社の2階には、決算会見などに使うための大ホールがある。経営方針説明会など大きなイベントが開かれると、100人を優に超えるメディアの記者やカメラマン、証券アナリストなど多くの人たちが押し掛ける。
その会場で最近、やたらと漏れ聞こえる言葉がある。それが冒頭の「既視感(デジャブ)」だ。
ソニーは言うまでもなく、日本人のみならず、海外の人々からも特別に愛され続けてきた。
だからこそ、会場に集まった参加者たちは、壇上の経営者が発する言葉を聞き逃すまいと一言一句をメモにする。必死でパソコンのキーボードを打って速報したり、その表情をシャッターで切り取るため息を止めるのだ。
「週刊ダイヤモンド」でソニーを3年間にわたって担当してきた取材チームも、その思いは同じだ。
ところが、どんなに耳を澄ませても、現在の平井CEOをはじめとした経営陣からは、まるで空疎なキャッチフレーズと、延々と繰り返される「弁明」しか聞こえてこない。それが既視感の原因だ。
一例を挙げるならば、過去4年間にわたるソニーの経営数字や主要商品の台数の「下方修正」の回数。本誌では3カ月の業績発表をもとに並べた表を掲載しているが、市場に対する公約がいかに守られていないか如実にわかる。
これを見れば、それがソニーの現役社員であっても「えっ」と驚きの表情を浮かべるはずだ。赤い下向きの矢印は、まるで巨大な滝が、轟音を立てて、とめどなく落ちてゆくように見える。
そして、あまりにも軽い経営者の言葉だ。長年課題のテレビ事業をめぐる発言を振り返ろう。
「(テレビ)赤字の責任は、チームを一新し、事業本部を刷新した」(2011年度第2四半期決算)
「必ずや黒字化する。テレビ事業再生のため、最終兵器をついに投入しました」(12年3月、ソニーグループ臨時部長会同)
「私は与えられた使命、つまりエレキのターンアラウンドをやり遂げる」(13年度第3四半期決算)
本人たちにも、既視感があるのかもしれない。
後見役の加藤優前CFOは「連続下方修正の回数は4回ではなく、3回ではないか」とメディアに反論したものの、実は4回が正しかったという、財務責任者としては信じられない発言までしでかした。
ソニーが抱える本当の病巣は、本質的な経営再建と向き合わず、弁明にばかり終始する「延命経営」にあるのではないか。
弥縫策の全容を
余すところなく抉り出す
『週刊ダイヤモンド』4月26日号で「ソニー消滅!! 尽き果てる“延命経営”」を特集しました。
家電の雄であり、世界を席巻したソニーが、負のスパイラルから抜け出せないままでいます。同じく苦境に陥りながら、大胆な選択と集中でⅤ字回復の軌道に載せたパナソニックと比べると、その差は際立つばかりです。
なぜ、ソニーは不振から脱却できないのか。本誌では平井CEOをはじめとした現経営陣の延命経営ともいえるビジョンのなさに、その主因を見いだしました。
本業であるエレクトロニクス事業復活に力を注ぐよりも、本体の延命、いや現経営陣の自己保身のために、資産をたたき売り、子会社までもしゃぶり尽くそうという究極の弥縫策の全容を、余すところなく抉り出しています。
もちろん、ソニーがそのまま敗れ去るとは思っていません。再建を託された男たちにもフォーカスし、人物像に肉薄しました。ソニーの創業地近くで、モノづくりの遺伝子を引き継いだ“ヤメソニー”たちの挑戦も取り上げています。
担当記者が昼夜を別たず取材に駆けずり回り、膨大な資料を読み込んで分析した上で、魂を削りながら書き上げた特集です。今回の特集に対する彼らの熱い思いをつづったWeb限定のスペシャルコンテンツ「なぜ、私たちはソニーを書くのか」も用意しました。こちらも併せて、ぜひ一読ください。
(『週刊ダイヤモンド』編集長 田中 博)
今号のお買い求めはこちらからもできます。
本誌2014年4月26日号
「ソニー消滅!! 尽き果てる”延命経営”」