定期購読でしか手に入らない
信頼と実績のビジネス情報源
いつでも最大30%オフ、デジタル版も無料!
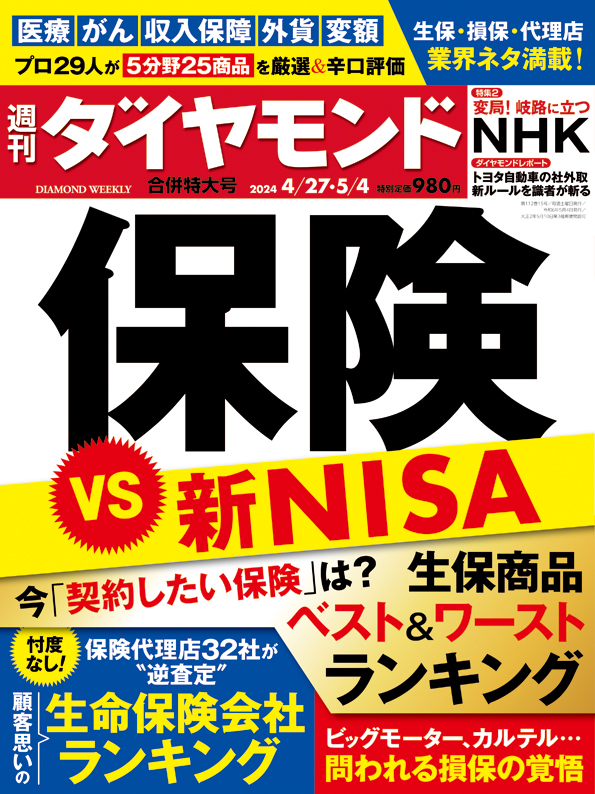
いつでも最大30%オフ、デジタル版も無料!
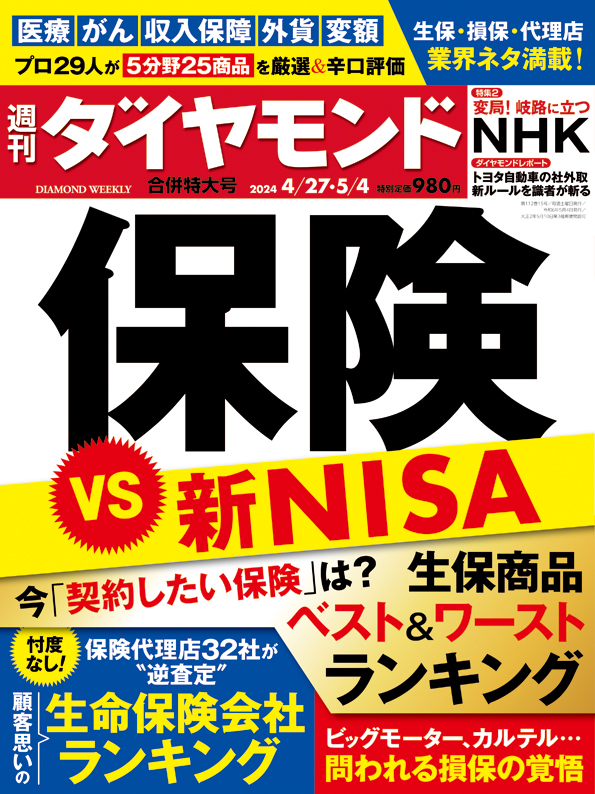
Benefits
01
通常1冊1,320円のところ、3年プラン(108冊)なら1冊あたり917円(30%オフ)の大幅割引。続けて読むほど断然お得です。

02
日本全国どこでも送料無料。毎号、発売日当日にご自宅やオフィスなどご指定の住所へお届けします。ポスト投函方式のため対面での受け取りも不要です。

03
最新号、直近のバックナンバー4冊をデジタル版でもご提供。発売前週の金曜日に更新されるので、いち早く本誌をお読みいただけます。

04
ダイヤモンド社が主催する各種セミナーやイベントにご招待。ビジネス、教養、エンタメ等、バラエティ豊かな企画をご用意しています。

05
全国のホテルやゴルフ場をはじめ、ショッピング、スポーツクラブ、レジャー施設等、約7,000以上の提携サービスを特別優待価格でご利用いただけます。

Plans
1年プラン 36冊
市価概算 47,520円のところ
38,000円(税込)
3年プラン 108冊
断然
お得
市価概算 142,560円のところ
99,000円(税込)
※割引率は通常定価1,320円/冊と比較した場合
週刊ダイヤモンド定期購読と
ダイヤモンド・プレミアムの
お得なセット!

ダイヤモンド・オンラインの有料会員限定記事や厳選したダイヤモンド社ベストセラー書籍、The Wall Street Journalの日米中3カ国版が読める「ダイヤモンド・プレミアム」は週刊ダイヤモンド定期購読とのセットがお得です。
\ 新規で定期購読をご検討中の方 /
セットプランに申し込む\ 定期購読をご利用中の方 /
About
週刊ダイヤモンドは今から100年以上前、創業者・石山賢吉の手により創刊。「本誌は是とするも非とするも総て算盤に拠り、算盤を離れて何物も無い」という創刊時の言葉通り、数字と事実に基づいた洞察で、ビジネスパーソンの公私に役立つ情報をお届けしてきました。読者層の中心は、経営者・役員クラス。他のメディアとは異なる独自の切り口で、広く支持をいただいています。
Precaution
Consultation
受付時間 : 平日 9:30~17:30 / 土日祝休み
平日夕方はお電話が混み合う場合がございます。
あわせて「お問い合わせフォーム」をご利用ください。